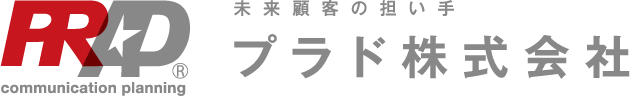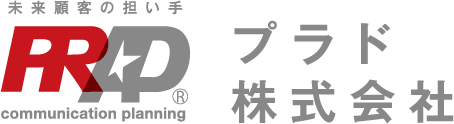今、変わるべきでしょ!可藁津今茂の経営日記
title
曖昧でも大丈夫?
「曖昧さ耐性」と言語化の力
月に1〜2回、経理作業で実家に帰ると、父・可藁津今茂(68歳)とのお茶時間が自然に始まる。
この日も書類を片づけていると、父がぼそっと言った。
「まぁ、大体でええんや。昔からそんなもんやろ」
私は思わず笑ってしまった。
「でも曖昧でも大丈夫って思うのって、本当に大丈夫かな?」
父は「そら、人を信じとるからや」と肩をすくめる。
そこから私たちの会話は、「曖昧さ耐性」というテーマへ進んでいった。
曖昧さ耐性とは?
人は時に「細かく決めなくても進むやろ」と思いたがる。
理由は様々だ。
・書面にするのが面倒だから
・信じているから確認を省きたいから
・雰囲気を壊したくないから
父の世代は、職人同士で「阿吽の呼吸」でやり取りをしてきた経験が強い。
「顔合わせて『わかったわかった』で通じとったんや」
そう語る父の表情には、自分の時代の誇りがにじむ。
曖昧さが生む落とし穴
けれど、曖昧なままでは誤解が生まれる。
「数量はこのくらいで」「納期は目安で」
そういうやりとりが積み重なれば、後で「そんなつもりじゃなかった」と揉める原因になる。
私は父に言った。
「言語化って、曖昧なことを“具体”に変えることなんだよ」
父は「せやけど、曖昧さがええときもあるやろ?」と返す。
「人間関係では柔らかさも大事だよ。でも仕事では記録にしないと誤解を生む」
言語化の必要性
曖昧なままにせず、言葉にすることは「不安を取り除く作業」でもある。
・曖昧を具体に変えることで、相手がどこまで理解しているか確認できる。
・責任の所在も明確になる。
・何より「確認をしても信頼が揺らがない関係」を築ける。
「信じてるから確認しない」のではなく、
「信じてるからこそ確認を惜しまない」。
それがこれからの時代に求められる信頼の形だと思う。
今回の気づき
曖昧さ耐性は気楽に見えて、実際にはリスクをはらんでいる。
だからこそ「曖昧を具体に変える=言語化」が欠かせない。
言葉にして残すことは、相手を疑うからではない。
むしろ、信頼を守り、長く関係を続けるための誠実な行動なのだ。
この物語はフィクションですが、実際の経営現場でよくある話をもとにしています。