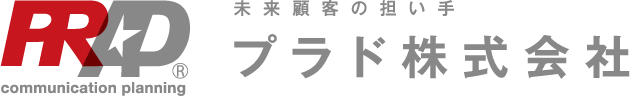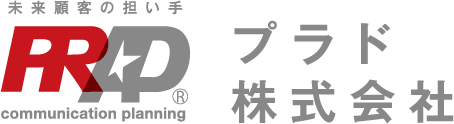採用強化
RECRUITMENT
言語家が考える採用強化。採用成功と企業理念の本質的連動
経営者の方に伝えたい。採用強化は理念から始まる会社づくりのチャンス
多くの企業が「人手不足」や「採用の難しさ」に直面している今、採用活動を見直す中で「経営理念の重要性」に気づく経営者が増えてきました。ただしここで、経営者の皆さまにぜひお伝えしたいのは、「採用のためだけに理念を作るのは本末転倒である」ということです。理念は、企業の採用力を高めるだけでなく、会社全体の在り方を見つめ直す絶好の機会でもあります。
安易に「採用対策」として理念を掲げるのではなく、このタイミングで改めて自社の存在意義や未来像を言語化し、それを軸にした会社づくりを進めていくことで、社内外に一貫したメッセージが伝わり、結果として求職者からも「魅力的な会社」と認識されるようになります。採用成功の裏側には、確固たる企業の姿勢と価値観の共有があります。理念は「人を集める道具」ではなく、「人が集まる理由」であるべきなのです。
採用活動の出発点としての経営理念。人材のミスマッチを防ぐ柱として
中小企業の経営者からは、「採用活動を強化したいから経営理念を作成した」という声をよく耳にします。たしかに、採用市場において目立つために「経営理念を掲げる」ことは一つの手段です。しかし、もし経営理念が「採用目的のためだけ」に作られているとしたら、それは言語家としての本質から外れています。経営理念とは、企業の価値観や進むべき方向を示す「経営の軸」です。採用活動のためだけの装飾ではなく、意思決定の基準や社内文化づくりにも深く関与するものでなければなりません。
経営理念を策定すること自体には非常に大きな意義があります。その目的は採用活動だけではありません。例えば、社内の意識統一、日々の経営判断の基準策定、組織文化の醸成など、多岐にわたります。これらがしっかり根付き、企業文化として定着していくことで、採用時に「理念に共感してくれる人材」の募集が可能になります。結果として、人材採用において「人材のミスマッチ」を防ぎ、持続可能な組織成長へつながるのです。言語家としては、採用活動の文脈においても、本質的な理念づくりとその活用を強く推奨します。
提灯理念
言語家が作った『形だけの経営理念』のことを表現した言葉
採用でありがちな「見せかけの理念」が招く失敗
「提灯理念」とは、言語家が名付けた造語で、まるで提灯記事のように企業を美しく見せるためだけを目的にした内容の伴わない経営理念を、私たちは「提灯理念」と呼びます。
こうした表層的な理念では、採用活動において「人材のミスマッチ」を避けるどころか、むしろミスマッチを引き起こす原因となります。理念に中身がないと、求職者は見た目の印象で応募してしまうため、結果的に価値観のずれが生じ、「採用してから期待とのズレが大きかった」という事態を招きやすくなるのです。
外部の採用支援会社やコンサルタントから「採用強化のために経営理念を作りましょう」と言われた場合には、その背景や意図を慎重に確認することが重要です。理念は本来、経営者の想いを可視化し、社内外に発信するためのもの。これが「採用ツール」のような表面的な目的だけで作られてしまうと、結局は「人材のミスマッチ」を減らすどころか増やす結果になりかねません。
採用で成果を出すための理念の役割。理念浸透と求人情報の設計
採用強化を真剣に目指すのであれば、まずは社内で経営理念を徹底的に浸透させることがスタート地点です。人事や経営層だけでなく、現場の社員に至るまで「この理念が自分たちの行動指針である」という共通認識を持たせることが欠かせません。
そして、その企業理念に共感してくれる人材をターゲットとした求人情報を設計します。理念を起点とし、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を求人広告や採用ページの文言に反映することで、求職者にとっても「共感できる会社であるかどうか」が分かりやすくなります。
こうして「価値観ベースの採用」が実現すれば、採用時点でのミスマッチは確実に減ります。たとえ採用人数が少なくても、「理念に共鳴した人」が入社し、定着率も向上し、チーム全体の生産性やモチベーションにもポジティブな影響が出ます。
採用とは「人数を揃えること」ではなく、「共に歩める仲間と出会うこと」。だからこそ、理念を起点とした設計が、人材のミスマッチを芽のうちに摘む鍵になるのです。