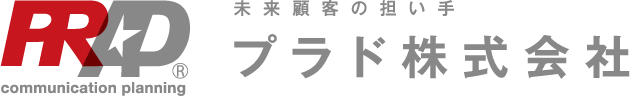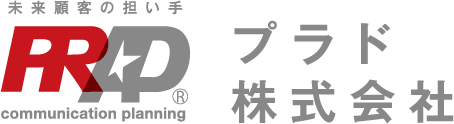今、変わるべきでしょ!可藁津今茂の経営日記
title
不便さが教えてくれること
月に1〜2回の経理作業で実家に帰ると、父・可藁津今茂(68歳)はまだ片手にサポーターをつけていた。
少し前に手首を痛めてから、ギプスが外れて今はサポーター生活だ。
「もうだいぶええけどな、まだ力入れるとズキッとするんや」
そう言いながらも、父は伝票を手にして私に渡してきた。
思えば、父がギプスをしていたときは、周囲の反応がとても分かりやすかった。
社員からも親戚からも、すぐに「社長、大丈夫ですか?」と声をかけられる。
見た目に「怪我をしている」と分かるから、自然に気遣いが生まれるのだ。
ところが、ギプスからサポーターに変わると、様子は少し違った。
パッと見は元気そうに見えるからか、「もう治ったんですか?」と軽く言われることが増えた。
まだ不便なのに、そう見えないことで気持ちのギャップが生まれる。
父はそれを少し寂しそうに話していた。
「人って、見た目で判断するんやな。まあ、しゃあないけど」
私はその言葉を聞きながら、「確かにそうだ」と思った。
普段、健康なときは当たり前のように手を動かし、歩き、仕事をしている。
でも、一度不自由になってみると、その“当たり前”がいかに支えられていたかがよく分かる。
「ありがとう」という言葉が増えた
父が怪我をしてからというもの、家の中でも会社でも「ありがとう」という言葉が増えた。
茶碗を持ってきてもらって「ありがとう」
伝票を書き写してもらって「ありがとう」
重い部品を持ち上げてもらって「ありがとう」
今までなら無言でやっていたことが、不便さゆえに「助けてもらっている」と意識される。
そのたびに「ありがとう」が口から出る。
父も照れくさそうに笑いながら言った。
「ほんま、怪我してみて分かるわ。わし、今までありがとう言わんでええと思っとったんやな」
その一言に、私は少し胸が熱くなった。
『ありがとう』は小さな言葉だ。
でも、その積み重ねが人間関係を柔らかくする。
社員との距離も、家族との距離も、きっと変わっていく。
父はこれまで「仕事はやって当たり前」「責任を果たすのが普通」と思ってきた。
だから感謝の言葉を省略してきたのかもしれない。
でも、不便を抱えて初めて「助けられていること」に気づいたのだ。
私は、後継者の立場からもこの話は大きなヒントだと思う。
経営は数字や仕組みだけでなく、人と人との信頼の上に成り立つ。
その信頼をつくるのは、大げさなことではなく日々の「ありがとう」かもしれない。
会社を続けるには技術や営業力も必要だけど、人の心を動かすのはやっぱり感謝の言葉。
父の姿を見ながら、私自身ももっと素直に「ありがとう」を伝えようと思った。
今回の気づき
不便を経験すると、支えられていることに気づける。
「ありがとう」を言葉にすることは、人を動かし、関係を強くする力になる。
この物語はフィクションですが、実際の経営現場でよくある話をもとにしています。