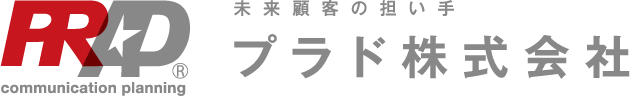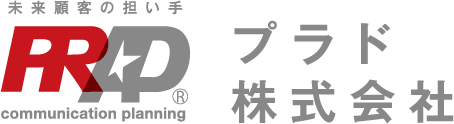理念やビジョン、経営指針書の用語集
rinen
経営理念やビジョン、経営指針書の用語を解説します
経営理念とは
経営理念とはミッションを実現していくために、会社として大切にするべき価値観のことを言います。
簡単に言えば、木の根っこと言えばイメージしやすいと思います。
経営理念があることのより、社業などいかに振舞うかの軸となったり、行動や判断の基準となります。
経営理念が無ければ、軸がないためブレた判断をしてしまいます。
経営理念の浸透とは
経営理念の浸透とは、会社が掲げた経営理念を組織の一員である誰もが理解し、共感した状態で経営理念に相応しい行動を実践している状態を指します。
経営理念が浸透すると、社員の行動が変わります。経営理念が浸透された行動により提供される商品やサービスの内容や対応など変わります。その結果、株主、取引先、仕入先、金融機関、行政機関、各種団体、地域などの利害関係者にも経営理念が浸透し共感が深まります。
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは
MVVとはミッション・ビジョン・バリューの英語の頭文字を合わせた言葉です。
ビジョンとは
ビジョンとは「目標、夢、志、方向性」などと訳される言葉。組織が目指す将来の理想の姿といえます。
簡単に言えば、弓の的と言えばイメージしやすいと思います。
ミッションで定められた存在意義に基づいて事業を行い、将来的に「会社が将来こうなりたい、こうしていきたい」という組織や社会の姿を具体的に示すものです。
ビジョンは中長期(3年、5年、10年)など期間を定める場合があります。
営業のあり方とは
営業のあり方とは、顧客目線の視点を重視してビジョンの中でも究極的な位置づけとして定める言葉として定義をしています。北極星をイメージしてください。北極星を目指して航海をしますがたどり着く場所ではないはずです。企業としてどんな存在になっていくかと目指すべき姿のことを指します。
また、営業というのはセールスと感じられるかもしれません。こちらで表現する営業とは、事業の営みという広い視点の営業を意味しています。
この言葉は弊社が定めた言葉です。
経営者、経営陣、従業員にお客様にこう在りたいという目指すべき姿 究極的な目標として掲げて頂いています。
経営指針書とは
経営指針書とは会社が発展するための道筋を具体的に描き書面化したものです。
経営理念、ビジョン、経営基本方針、経営計画を指針としてまとめたものを指します。この指針を成文化したものを経営指針書と言います。
経営指針書を特に従業員に周知して会社の発展を協力してもらうことが必要となりますので、作成して机の中にしまいっぱなしではいけません。
経営者が未来を描くためのお力になれればと思います。
経営指針発表会とは
1年に1回定期的に経営指針書を社員に発表する取り組みを経営指針発表会と言い、会社が目指す方向性を会社全体で共有します。
提灯理念
提灯理念(ちょうちんりねん)とは、言語家® 宮下孝が提唱した言葉であり、企業や組織が掲げる理念が 実態を伴わず、見かけや体裁を整えるためだけに存在する状態 を指す。
外向けの印象づくりや形式的な掲示を目的としてつくられる一方で、真の理念としての浸透や定着がなされていないため、組織の実際の行動や文化には反映されません。
特徴
■形骸化(けいがいか)
・言葉として掲示されているだけで、実際の経営判断や社員の行動指針には活かされていない。
・会議室やパンフレットに「額縁」として飾られて終わる。
■額縁化(がくぶちか)
・オフィスの壁やホームページに載せること自体が目的化しており、中身の活用は二の次。
・「あること」が重要視され、「浸透すること」は軽視される。
■外向き主義
・採用広報や営業用のスローガンとしては使われるが、内部の行動や意思決定に影響を与えていない。
・「提灯記事」のように、飾りや宣伝の要素が強い。
| 観点 | 提灯理念 | 真の理念 |
|---|---|---|
| 目的 | 外部への見せ方・体裁づくり | 内部で活き、外部へも自然に伝播する基軸 |
| 主眼 | ホームページ・パンフレット・採用資料で映える言葉 | 社員が日常で使い、結果的に外へ伝わる言葉 |
| 効果が出る対象 | 外部評価(取引先・求職者・展示会来場者) | 社員・経営層・組織文化、さらに顧客や社会へ |
| 特徴 | 華やかで耳触りが良い、見せるために増やされがち | シンプルで本質的、使われることで磨かれる |
| 浸透のしやすさ | 額縁化・形骸化しやすい | 内部に根づくと、自然と外部にも広がる |
| リスク | 社員から「外向けのきれいごと」と見られる | 形にするまで時間がかかる(だが長期的効果大) |
| 成果物 | 「理念が立派に整っている会社」という印象 | 「理念が行動に根づき、社内外に響く会社」という実態 |