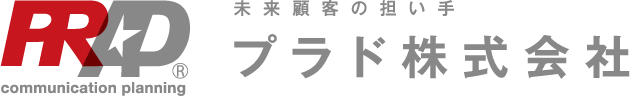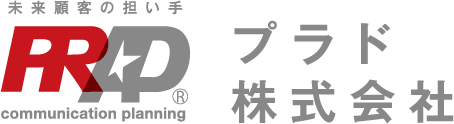今、変わるべきでしょ!可藁津今茂の経営日記
title
代わりがいないことの怖さ
月に1〜2回、経理作業のために実家に戻ると、父・可藁津今茂(68歳)はまだサポーターを巻いた手首を庇うようにしていた。
「まあ、動かんことはないけどな。やっぱり片手使えんと、何するにも不便やわ」
そう言いながら、請求書の束を前に、ペンを持つ姿はぎこちない。
伝票にサインをするのも、品物を持ち上げるのも時間がかかっている。
その姿を横で見ていたら、不意に胸がざわついた。
「もし本当に父が動けなくなったら、この会社はどうなるんだろう?」
社長不在の現実
父はこれまで40年以上、この町工場を回してきた。
仕事はもちろん、取引先との付き合い、地域のつながり、社員とのやりとり・・
すべてが社長である父を中心に成り立っている。
社員は15人ほど。みんな腕は確かで、父のもとでずっと働いてきた人たちだ。
でも、経営の判断や外との折衝は、どうしても父に頼り切りだ。
「社長がいなかったら、回らんのちゃうか」
そんな言葉を社員が口にしているのを耳にしたことがある。
そのときは冗談交じりに笑っていたけれど、今は笑えなかった。
父自身も少し弱音を漏らした。
「わしが抜けたら、この仕事、どうなるんやろなあ…」
普段は強気な父がそんなことを言うのは珍しい。
きっと怪我をして、思うように動けない今だからこそ出た本音なんだろう。
私は名古屋で別の会社に勤めていて、まだ父の会社を継ぐと決めているわけではない。
正直に言えば、「私がやる」とまではピンと来ていない。
でも、今のままでは会社が危ういことは分かる。
代わりがいない、バトンが渡されていない・・それが現実なのだ。
中小企業の課題
このことは、父の会社だけの話ではない。
中小企業の多くが同じ課題を抱えていると思う。
経営者が高齢になり、後継者も決まらず、もしトップが病気や怪我をしたら一気に止まってしまう。
「社長の代わりはいない」
その言葉は誇りのようでもあるし、同時に危うさでもある。
誇りはオンリーワンの存在であること。
危うさは代替がきかない存在であること。
その両面を、今回の出来事で強く実感した。
私はまだ「自分が継ぐ」とまで思えてはいない。
でも、会社が父だけに頼っていることのリスクは否定できない。
せめて少しずつでも、経理や書類整理以外に関われる部分を見ていこう。
そう考える自分がいる。
父は「代わりがいない」存在であり続けたいのかもしれない。
でも、これからは「代わりを育てる」ことも経営の一部なんじゃないだろうか。
怪我という小さな出来事が、その現実を浮き彫りにしてくれた気がする。
今回の気づき
「代わりがいない」ことは誇りでもあり、リスクでもある。
未来のためには、代わりをつくる準備を始めることが必要だ。
この物語はフィクションですが、実際の経営現場でよくある話をもとにしています。