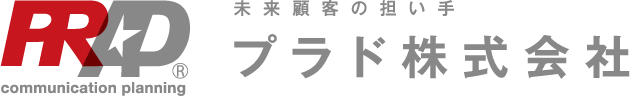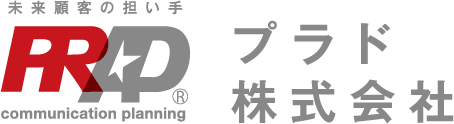共創連携団体 会社の環境整備
alliance
アライアンスによる共創と連携の力。製造業の未来を共に創る
ご縁を互いの円に。つながる、つたえる、うまれる
この団体にいることで、「つながる(出会い)」「つたえる(発信)」「うまれる(共創)」が日常になります。
展示会の場だけでなく、会員同士の協力によって新商品が誕生したり、実際に新たな販路を開拓できた事例もあります。他社の視点から商品を磨く機会が生まれたり、思わぬ業種との連携で受注につながったという声も届いています。
単なる利用ではなく、自社の可能性を広げながら、一緒に成長できる共創の場として活用していただけます。
団体名称
共創連携団体 会社の環境整備
主宰・事務局
プラド株式会社
活動内容
・展示会への共同出展
・本会内外への広報連携
・勉強会、交流会、忘年会などの人的交流
・有志による共同セミナー、開発、営業活動などの共創活動
参加企業
33社(2026年1月現在)
行動方針
・隣接異業種同士で交流し、連携推進を
・毎年の展示会は都度、参加を募る
・互いに発展を前提に
・パートナーとして選ばれるような会社を目指す
入会について
製造業を対象に募集中
費用について
入会金・年会費はありません
※交流会参加費用、共同出展費用等プロジェクトに応じて費用が発生します
製造業アライアンスの新たな挑戦
製造業界において、企業間の「繋がり」は単なる取引関係を超え、共に成長し合う「共創」の関係性へと進化しています。専門性を持つ企業同士が「互いに発展」を前提に行動し、連携を深めることで、新たな価値を創出するアライアンスが注目されています。このような取り組みは、製造業の「伝える力」と「繋がる力」を高めることに繋がります。
製造業内の異分野連携。新たな価値創造の場
製造業と一口に言っても、自動車関連、医療機器、精密機械、食品加工など、扱う分野やターゲットとする業界が異なれば、その世界観やニーズもまったく違ってきます。だからこそ、これまで関わりのなかった製造業同士が出会い、連携することで、思いもよらないシナジーや新たな視点が生まれます。
このアライアンスでは、あくまで製造業に特化したネットワークを築いていますが、その中でも分野をまたぐ「異分野連携」によって、各社が持つ専門性や技術を活かし合い、「共創」による新たな価値を創出することを目指しています。単なる協力関係ではなく、共に挑戦し、互いに発展していく関係性を築くことが、この取り組みの核となっています。
ネットワークの構築と強化。持続的な成長の鍵
製造業におけるネットワークの構築と強化は、持続的な成長のための重要な要素です。定期的な交流会やセミナーの開催、情報共有の場の提供などを通じて、企業間の信頼関係を築き、連携を深めていきます。このようなネットワークは、単なる情報交換の場を超え、共に課題を解決し、成長していくための基盤となります。
ご縁づくり。人と人との繋がりが生む価値
製造業アライアンスにおいて、「ご縁づくり」は非常に重要な要素です。人と人との繋がりが、新たなビジネスチャンスや協力関係を生み出します。このようなご縁は、単なる偶然ではなく、積極的な交流や情報発信によって築かれるものです。経営者の「伝える力」と「繋がる力」が、ご縁づくりの鍵となります。
製造業アライアンスの未来
製造業におけるアライアンスは、単なる協力関係を超えた「共創」の関係性を築くことが求められています。異業種団体との連携や展示会共同出展、ネットワークの構築と強化、ご縁づくりなど、多様な取り組みを通じて、企業間の信頼関係を深め、持続的な成長を実現していくことが重要です。経営者の「伝える力」と「繋がる力」が、これらの取り組みを成功に導く鍵となります。
アライアンスチームによる「会社の環境整備」
共創の基盤づくり
製造業の現場では、技術や経験が企業の競争力を左右する一方、今求められているのは、それぞれの専門性を活かしながら「連携」し、業界を超えた共創を生み出す環境整備です。私たちアライアンスチームでは、各企業が「互いに発展する」という共通認識を持ち、日々の取り組みの中で「繋がり」や「ご縁づくり」を大切にしています。
経営者同士が、自社の事業内容や強みを「伝える力」で共有し合い、親和性を探りながら協力の糸口を見出していく。こうしたやり取りを通じて、「繋がる力」が磨かれ、ただの取引先ではない、深い信頼関係が育まれていきます。
その中で、展示会への共同出展は、攻めの連携のひとつの形として大きな役割を果たしています。ものづくりの現場で日々研鑽を積んできた技術を、他社の製品と並べて紹介することで、訪問者にとっても一貫性のある提案が可能になり、新たなネットワークが広がるのです。これは単なる販売促進を超え、製造業の枠組みの中で異分野の企業が「繋がり」を生み出すきっかけとなっています。
プロジェクト会(以下、PJ会)では、各参加企業がそれぞれに役割を持ち、主体的に取り組むことを重視しています。単なる「参加者」ではなく「共創のパートナー」として、互いに支え合い、成果を出すことにこだわります。この継続的な積み重ねが、5年後、10年後にも同志として歩みを共にできる関係性の礎となるのです。
この取り組みは、決して短期的なメリットにとどまるものではありません。長期的に連携を続けられるネットワークを構築し、時には「攻め」の共同マーケティングや商品開発を、時には「守り」のBCP支援のようなリスク分散策を実現できるような、真のアライアンス体制を目指しています。
アライアンスは、単なる集まりではなく、「共に創り、共に育ち、共に守る」もの。これが、私たちが目指す製造業の未来です。