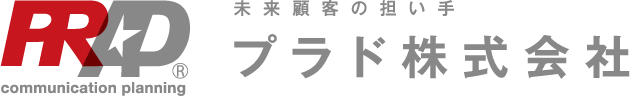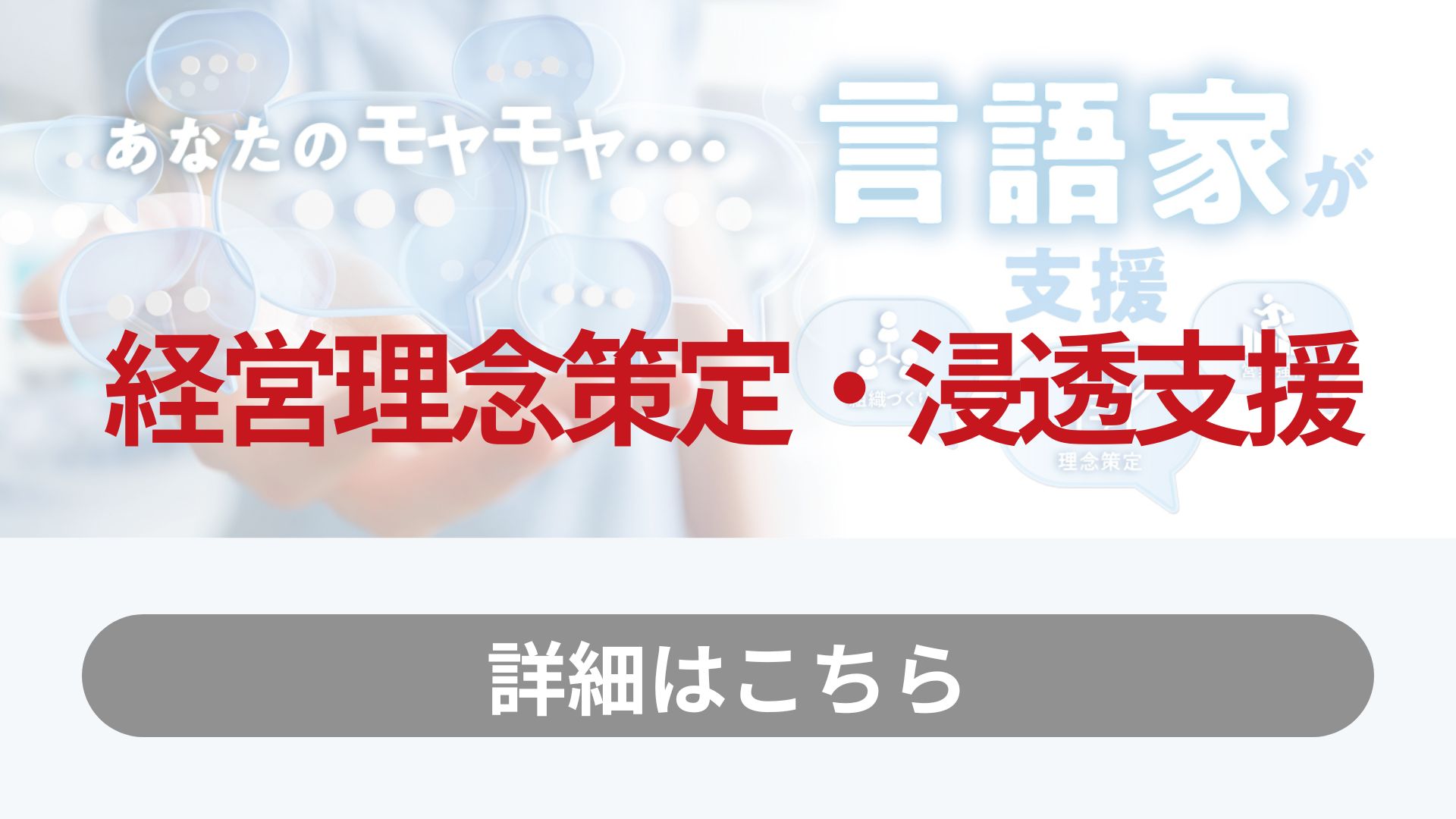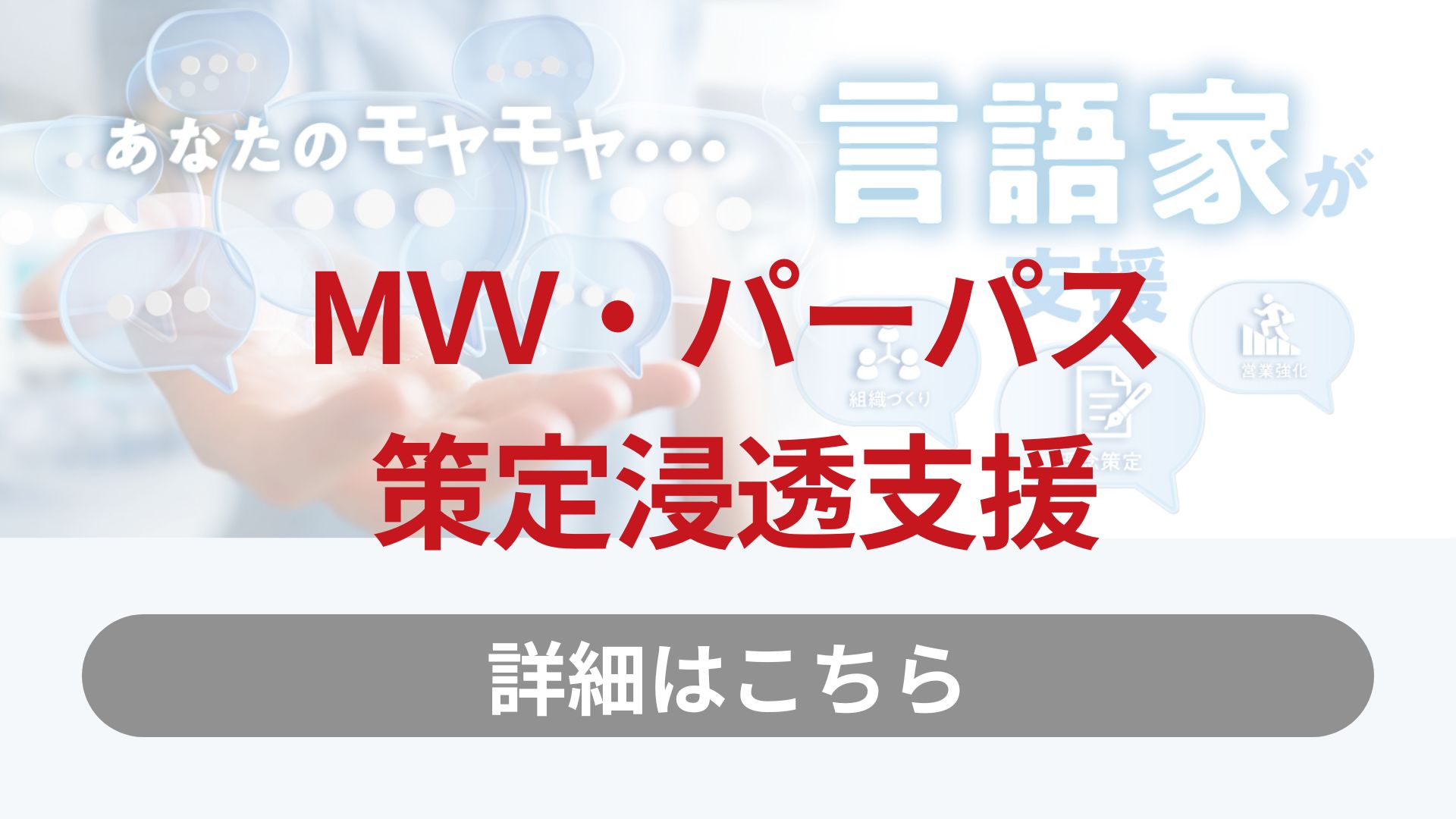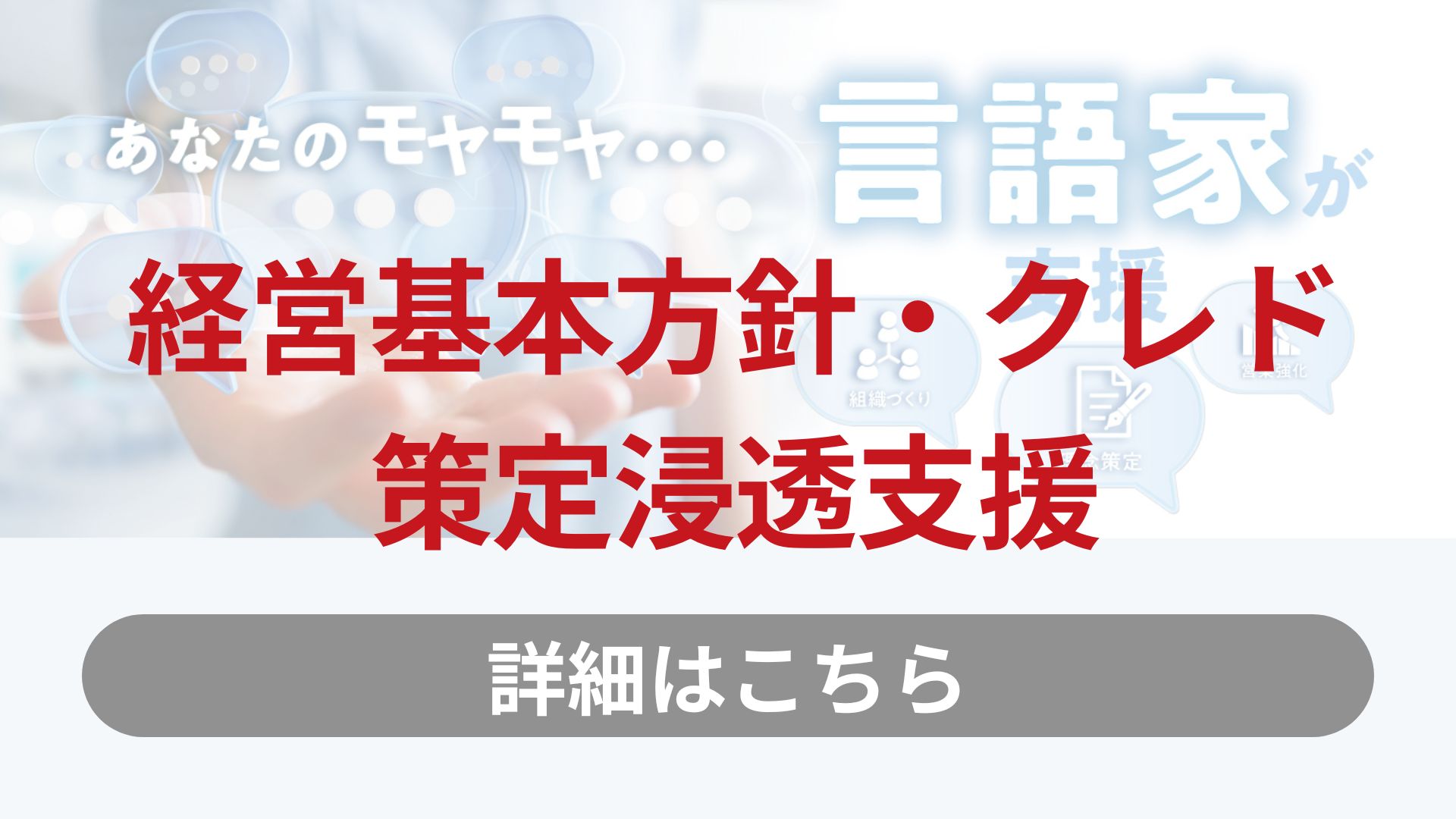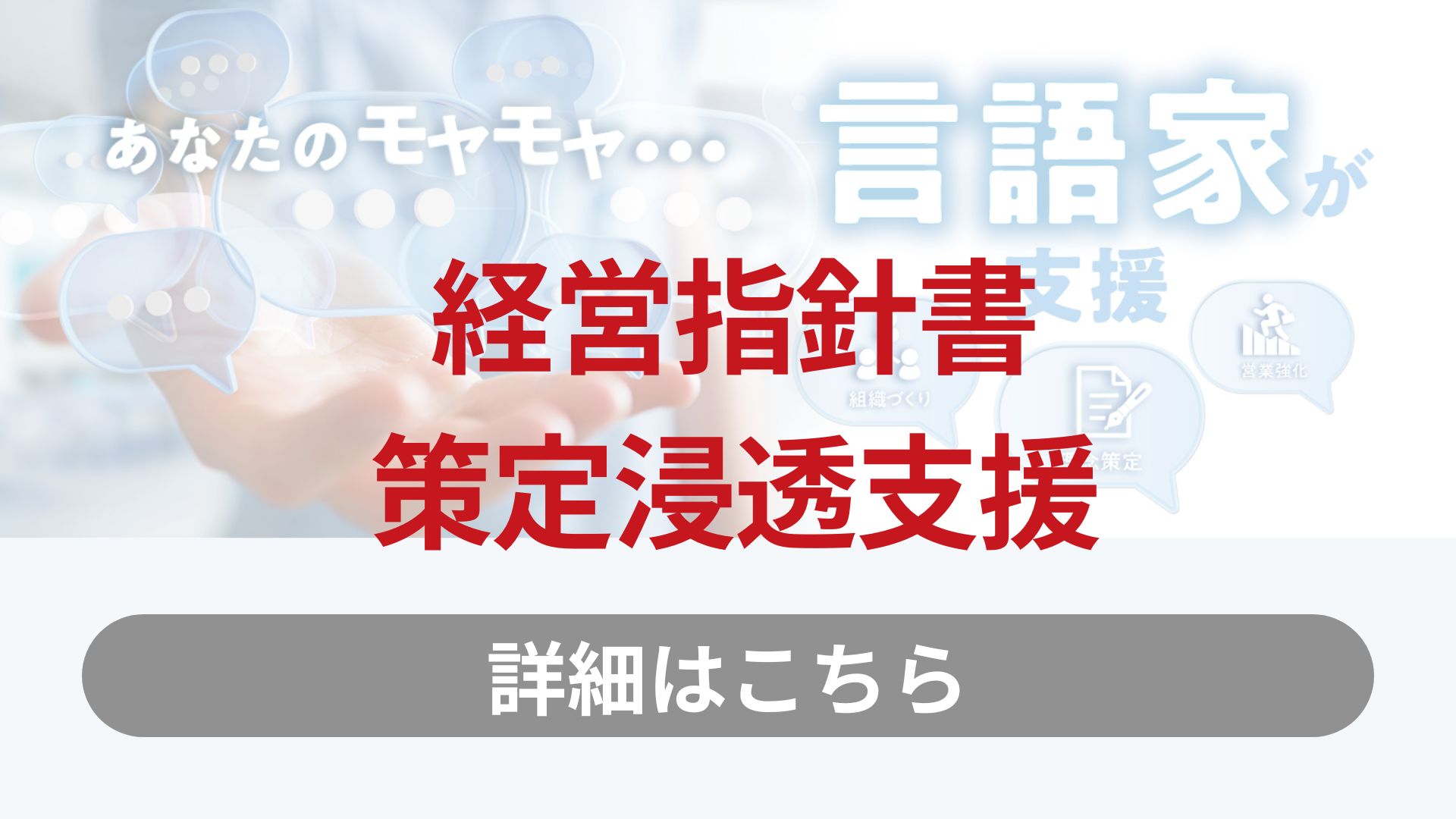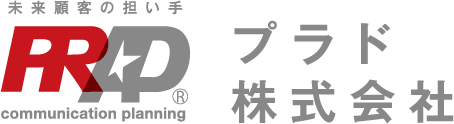理念・ビジョン・パーパス等について
formulation
はじめに|これからの経営に“言葉の指針”を
今、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。四半期ごとに前提が覆るようなスピード感、市場の不確実性(VUCA)の常態化、人的資本経営やSDGs・ESGの重要性の高まり──経営の現場は、これまで以上に複雑さを増しています。
こうした時代において、指針となるのは売上やKPIといった数字だけではありません。経営理念策定やビジョン策定、パーパス策定によって言語化された“経営の軸”が、日々の意思決定や組織の判断を支える力になります。さらに、これらを経営指針書に体系化し、経営理念浸透・ビジョン浸透・パーパス浸透を計画的に進めることで、経営計画や中期経営計画まで一本の線でつながり、現場での実装精度が高まります。
たとえば、こんな悩みに心当たりはないでしょうか?
・創業期から事業を成長させてきたが、自社の理念をうまく言葉にできていない
・後継者として経営を引き継いだものの、現状の事業や組織とどう結びつけるべきか悩んでいる
理念やビジョンが浸透することが意味がある
単にスローガンを掲げるだけでは、現場は動きません。理念やビジョンが“実際に使える言葉”として組織に浸透してこそ、行動が変わり、経営指針書や経営計画、中期経営計画といった実行プランにも筋が通ります。評価・採用・会議運営などの仕組みに落とし込んで初めて、経営理念浸透とビジョン浸透が意思決定の質を押し上げます。
さらに、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を共通言語として整えることで、採用・育成から顧客体験の設計まで、組織全体がひとつの軸で動けるようになります。私たちは、経営理念策定・ビジョン策定・パーパス策定から始まり、経営指針書の設計・運用、パーパス浸透・経営理念浸透・ビジョン浸透までを一貫して支援しています。地域や業界特性をふまえた中期経営計画の構築も含め、企業の“言葉”を実務に根づかせる仕組みをご提案します。
理念・ビジョン・パーパス|プラドのスタンス
経営理念 ~「ご縁ある全てに顧客創造を」~
私たちが大切にしているのは、一つひとつの“ご縁”です。
お客様、社員、取引先、地域の方々──あらゆるつながりから、共に価値を生み出していく。
そんな思いを「ご縁あるすべてに顧客創造を」という言葉に込め、経営理念として明文化しました。
この理念は、単なるスローガンではありません。
投資判断や人材採用、商品・サービスの品質基準といった実務のあらゆる場面で、「私たちらしい選択かどうか」を見極める“ものさし”になります。
だからこそ、経営理念策定と同時に、それを日々の経営に落とし込む仕組みが重要です。
経営会議での活用、人事評価や育成制度への反映、社内コミュニケーションの運用を通じて経営理念浸透を図り、経営計画との間にもブレのない一貫性を持たせます。
パーパス 「未来顧客の担い手」 ~営業のあり方として定義~
「営業とは、未来のお客様を生み出し続ける仕事である」
これは、プラド株式会社が長年にわたり大切にしてきた考え方です。
近年、“パーパス(存在意義)”という言葉が一般化しましたが、私たちはその概念が広まる前から、多くの経営者と共に「営業のあり方」を言語化し、実務に落とし込む支援を行ってきました。
お客様の顧客、そしてその先にある“未来の顧客”の創出に貢献することこそ、営業の本質と捉えています。
現在では、この考えを企業のパーパスとして明確に位置づけています。役割は主に2つあります。
1、意思決定の基準となる“判断軸”としてのパーパス浸透
2、ビジョン策定と連動した提供価値の再定義
このアプローチによって、営業活動が単なる数字目標ではなく、「誰のために・なぜ存在するのか」という言葉で語られるようになります。結果として、案件獲得や顧客との関係構築のプロセスが明文化され、経営指針書の中で運用できる実践的な手順へと落とし込まれていきます。
ロゴと社名の由来|「プロモーション・アナログ&デジタル」
泥臭さとテクノロジーの融合を、経営の現場に。
プラド株式会社は、創業期に広告代理店として事業をスタートしました。
現場で泥臭く向き合う“アナログ”の感性と、効率的に広げる“デジタル”の技術。
そして、想いを形にして届ける“プロモーション”の発想。
この3つの要素を組み合わせる思想を、私たちは社名とロゴに込めています。
この価値観は、現在のサービスにも受け継がれています。
たとえば、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の言語化や、経営指針書・中期経営計画の運用においても同様です。
まず、対話(アナログ)を通じて、経営者や現場のリアルな声から本質を掘り下げます。
次に、ドキュメントやダッシュボード(デジタル)を使って、社内で共有・更新できる状態に整える。
そして、プロモーションの視点で、言葉や仕組みが“伝わる・動かせる”ものになるよう設計します。
理念から経営計画までを一貫させることで、組織が迷わず動ける基盤をつくります。
理念浸透の独自ノウハウ
言語家という専門性(言語化の専門家による支援)
言語家の役割
経営者の頭の中には、日々の経験や判断の積み重ねから生まれた“思考の断片”がたくさんあります。私たちは、それを丁寧に引き出し、つなぎ合わせ、言葉として形にする専門家──それが「言語家」です。
ただ言い回しを整えるのではなく、経営者の思考の骨格や判断の癖を見極め、そこから経営理念策定・ビジョン策定・パーパス策定へと落とし込んでいきます。
言葉をつくるプロセスは、構造をつくるプロセスでもあります。だからこそ、その言葉は現場で使える。
経営理念浸透やビジョン浸透の土台となり、経営と現場のズレを埋める共通言語になります。
「カンパソ」の設計思想
「誰に、何を、どう届けるか」を一枚に──言葉と仕組みの設計
私たちは、顧客にとって“当たり前”と思える価値提供の形を、あらかじめ設計しておくことが大切だと考えています。
そのために、「誰に、どんな価値を、どの順番で届けるか」を一枚の構造に落とし込みます。
この設計は、MVVと事業戦略・採用・育成方針をひとつにつなげるベースになります。
オンボーディング資料や経営指針書の章立てとも連動し、企業全体が同じ地図を持って動ける状態をつくります。
地域や業態に合わせたアレンジも可能です。
・愛知の製造業では技術伝承を軸に、
・名古屋の専門サービス業では顧客対応の品質を中心に、
・岐阜の中小メーカーでは地域密着と開発スピードを両立し、
・三重の観光・物流業では人の動線と体験価値を整理するように。
構造自体は変えずに、地域や業種ごとに読み替えられる柔軟性を持たせています。
刷新と再定義を促すプロセス設計
「引き出す」支援スタイル|思考を掘り下げ、組織の言葉へ。
私たちの支援は、ワークシートの穴埋めや文章の代筆ではありません。
壁打ちやインタビューを通して、経営者の思考を深く掘り下げていきます。
日常的な口癖や意思決定の癖、判断の背景にある価値観──そうした“思考の断片”を拾い上げ、事実と意見の境界を丁寧に整理しながら、組織全体で使える共通言語へと翻訳していきます。
こうして整えた言葉は、経営計画や制度設計の文書にそのまま活用できるレベルで仕上げています。理念やビジョンが「言いっぱなし」で終わらず、実務と自然に接続できる。それが、私たちの言語設計のスタイルです。
明文化のスピード感|1か月で言語化、半年で運用設計まで
まず、原則1か月で経営理念とビジョンを明文化します。
そこから半年後の経営指針発表会をゴールに設定し、パーパス浸透・経営理念浸透・ビジョン浸透までを見据えた運用設計を並行して進めます。
たとえば、採用広報や評価制度への反映、中期経営計画の骨子づくり(KGI/KPI・重点施策・レビュー設計)なども同時に設計。経営指針書にすぐ使える形で落とし込みます。
地域によっては、設計の優先順位も変わってきます。
・愛知の製造業では現場マネジメントと技術継承に合わせた指標設計
・名古屋のサービス業では即戦力採用と育成を両立できる仕組みづくり
・岐阜、三重の中小企業では地域特性や人材流動性に配慮した設計
地域、業態に応じて柔軟に対応しながら、「理念から実行」までを一貫して支援します。
論理的構成力による言語化|初回提案で9割の経営者が即決。抽象論で終わらせない言語設計
私たちは、経営理念やビジョンの言語化において「抽象的で終わらないこと」を徹底しています。
経営者の思考をロジカルに整理し、定義 → 原則 → 行動指針 → 測定指標へと段階的に落とし込むことで、“使える言葉”として仕上げます。
このアプローチにより、初回提案の段階で9割の経営者が理念やビジョンの言葉を即承認。
そのまま経営理念浸透・ビジョン浸透の準備フェーズに移行できるため、最初の一歩を最短距離で踏み出せます。
言葉を整えることは、意思決定の精度を高めること。
こうして設計された言葉は、MVVと中期経営計画をつなぐ“共通の軸”として、組織全体の動きを支える役割を果たします。
言葉をつくって終わりではなく、使える仕組みに
プラド株式会社の支援は、ただ言葉を整えるだけではありません。経営者との対話を通じて理念や存在意義を掘り起こし、そこから経営指針書や中期経営計画へつながる“使える言葉”を設計していきます。
設立当初から、愛知・名古屋・岐阜・三重といった地域の企業に伴走し、それぞれの事業環境や人材課題に合わせた運用設計をサポートしてきました。
現場に根ざした支援を積み重ねてきたからこそ、今の実践型フレームがあります。
言葉で終わらせず、組織が“動ける仕組み”までつなぐ。
それが、私たちが大切にしているスタイルです。
サービス体系へのご案内
経営理念から経営指針書まで、一貫して伴走します。
企業の成長ステージや組織課題に応じて、理念やビジョンの“正解”は変わってきます。
だからこそ私たちは、経営理念策定・ビジョン策定・パーパス策定などの上流工程から、経営理念浸透・ビジョン浸透・パーパス浸透といった運用フェーズまで、分けずに一貫して支援しています。
支援の中核となるのが、経営指針書と中期経営計画の構造づくりです。多拠点展開や複数事業がある場合でも、章立てやレビュー設計を共通化し、組織全体で使える仕組みに落とし込みます。
・名古屋の多拠点企業では、拠点間の意思統一を重視した設計
・岐阜の製造業では、原価構造に合った重点施策の明確化
・三重の観光業では、季節変動に対応したレビューサイクルの調整
・愛知の自動車関連企業では、サプライチェーン全体を見据えたKPI設計
地域ごとの事情や業態の特性もふまえ、現実に使える仕組みを一緒につくっていきます。
経営理念策定・浸透支援|想いを言葉に、日常で使える仕組みに。
創業者や後継者の想いを丁寧に言語化し、日々の意思決定や人の動きと自然につながる理念へと整えていきます。
たとえば、経営者や幹部の言葉をもとに、理念の“骨格”を定義し、評価制度や会議体、採用導線やオンボーディング施策にまで接続。
さらに、いつ・誰が・どんな場面で理念を発信するかといった“浸透の設計”も具体化します。
理念が「壁に貼るだけ」で終わらず、現場で自然に使われていく状態をつくります。
ミッション・ビジョン・バリュー・パーパス策定
浸透支援存在意義と未来像を、組織全体の共通言語に
まず、企業の存在意義(パーパス)と未来像(MVV)を明文化し、社員としっかり共有するところから始めます。そこから、研修・1on1・評価制度など、日常のマネジメント動線に沿って言葉を展開。理念やビジョンが、現場で自然に使われる状態をつくります。
さらに、採用広報でも同じ語彙体系を用い、社内と社外のメッセージを統一。
たとえば、ある愛知県の企業では、MVVを基軸にしながら、愛知・名古屋・岐阜・三重の地域ごとの求職者ニーズの違いに合わせて打ち出し方を調整しました。
言葉を整えることは、採用にも組織運営にも効く“共通言語”をつくること。
私たちは、その土台づくりを支援しています。
経営基本方針・クレド策定浸透支援|現場で迷わない「行動の基準」を、言葉で揃える
現場での判断や行動にバラつきがあると、顧客体験や品質、安全管理にも影響が出てしまいます。
だからこそ、私たちは「どんな場面で、どう動くのが自社らしいか」を、言葉で明確に定義していきます。
誰か一人の感覚に頼るのではなく、チーム全体で共有できるように、表現の粒度を揃え、ブレのない行動基準として整理。その内容は、経営指針書の中にきちんと格納され、日々の業務に活かされる形で運用されます。
経営指針書策定・浸透支援|戦略も人材も、数字も行動も──すべてを一冊に
経営の方向性を言葉で整理し、理念から実践行動までを一本の線でつなぐ。私たちは、戦略・人材・数字・行動指針をまとめて設計し、ブレない意思決定を支える「経営指針書」として形にします。
たとえば、名古屋本社を中心に、愛知県内の工場や岐阜・三重の拠点を持つ企業では、拠点ごとに温度差や判断基準の違いが起きがちです。そうした中でも、四半期レビューや社内発表会の運用設計を組み込むことで、経営計画の共通軸を保ったまま現場が動ける体制をつくります。
策定はゴールではなくスタート。
理念 → ビジョン → パーパス → 基本方針 → 行動指針 → 経営指針書 → 経営計画/中期経営計画へと、段階的に結びつけることで、言葉が日々の経営判断に効く“実行力”へと変わります。
「つくって終わり」ではなく、「生かし続ける」まで伴走します
単なる「策定」で終わらせず、浸透と実践に結びつけることがプラド株式会社の特徴です。
以下のページでは、それぞれの支援内容を詳しくご紹介しています。
お問い合わせ
プラド株式会社では、以下のようなテーマに関するご相談を承っています。
・経営理念策定・経営理念浸透
・ビジョン策定・ビジョン浸透
・MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の構築
・パーパス策定・パーパス浸透
・経営計画・中期経営計画の設計・見直し
・経営指針書の作成・運用支援
たとえば「今ある理念や資料が現状に合っていない気がする」「会議や評価制度と理念がうまくつながっていない」──そんな時は、現在お使いの文書・経営会議・部門会議の流れ・制度を拝見しながら、必要な見直しポイントを一緒に整理していきます。
ちょっとした違和感やモヤモヤでも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。
経営理念策定を「言語家」に依頼する意味とは?
「理念は自分たちで考えるべき」──その考えを、私たちも尊重しています。
ただし、経営理念策定・ビジョン策定は、“考える力”だけでなく、“言語化・構造化の技術”が問われる作業です。
どんなに良い想いがあっても、伝わる形にできなければ、組織には届きません。
自力で進めた場合に起こりがちな課題
・自社の「当たり前」に引きずられて、視野が狭くなる
・多様な価値観をうまく言葉に落とし込めない
・議論が長引いて、経営判断が後ろ倒しになる
・語感は良くても、実行に結びつかないフレーズになる
そこで、言語化と構造化の専門家である言語家がサポートに入ることで、プロジェクトが一気に前進します。
私たちは、経営者や幹部の方々との壁打ちを通じて思考を深掘りし、価値観・行動指針・将来像を整理。そこから経営理念・ビジョン・パーパスを明文化し、必要に応じて経営指針書や中期経営計画に接続していきます。
通常、1か月で言語化を完了し、その後の経営指針発表や施策展開までを逆算して設計します。
共創から生まれる、「経営を動かす言葉」
言語家の関わりは、アウトソーシングではありません。内省と対話を通じて、企業の核心に触れながら、理念や方針を“経営の言葉”として共に紡ぐプロセスです。
キャッチコピーではなく、組織を前に進める「軸」ができる。
その言葉があるからこそ、採用・育成・制度設計・発信に迷いがなくなり、経営そのもののスピードと精度が高まっていきます。
他社との違いは「書かせる」ではなく「引き出す」支援スタイル
1か月で経営理念は策定|経営理念は、1か月で“引き出し型”で仕上げる
経営理念を自作しようとする経営者の方は少なくありません。
フォーマットに沿って自分で書き出していく「自作型」は、考えを整理する上で確かに意味があります。ただその一方で、完成までに時間がかかりすぎたり、表現の質にバラつきが出やすいのも事実です。
私たちが採用しているのは、「抽出型」のアプローチ。
経営者や幹部との壁打ちを通じて思考を引き出し、私たちがそれを編集・構造化して言葉にまとめていきます。ひねり出す必要はありません。約1か月で、経営理念とビジョンの中核が整います。
ここで整理した言葉は、そのまま経営計画や中期経営計画の骨組みとして活用可能。さらに、MVV・評価制度・採用広報へ同じ語彙体系で展開できるため、部署間のズレも起きにくくなります。
この抽出型の特長は、「会社の実態」や「経営者の思考のクセ」を汲み取りながら、言葉が企業文化として根づく粒度に仕上げられること。
単なる代筆ではなく、“らしさ”のある表現を一緒につくり上げるプロセスです。
言葉は、文化をつくります。
だから私たちは、整理した言葉が評価・採用・育成・営業にまでつながる設計まで見据えます。
たとえば──
名古屋圏の多職種採用では職種ごとに伝える軸を調整
岐阜・三重の地域採用では、地元志向や価値観の違いを踏まえた伝え方へ最適化
このように、言葉を整えることは、経営そのものの土台を整えること。
私たちは、理念などの言語化の専門家(言語家)として、企業の「想い」を“動かす力”に変える支援を行っています。
経営理念・ビジョンは掲げるだけでなく、使うためにある
経営理念やビジョンは、掲示しただけでは機能しません。本当に大切なのは、それが日々の意思決定・行動・組織運営にどう活かされるかです。
その核となるのが「経営指針書」。
理念・ビジョン・パーパスに加えて、経営基本方針・行動指針・中期経営計画までを一冊にまとめ、組織全体の共通の土台として機能させます。
レビュー頻度・責任者・判断データの定義まで決めておくことで、言葉が“動かす仕組み”になります。
そして何より重要なのは、経営者自身が理念の体現者であること。
トップの言葉と行動が一致してこそ、社員の共感が生まれ、理念・ビジョン・パーパスは社内に浸透していきます。
経営指針書は再出発の共通言語になる
私たちのゴールは、経営理念やビジョンをスローガンで終わらせることではありません。言葉を形にして、組織を動かすための「経営指針書」としてまとめあげることです。
経営指針書の意義
・経営不振や方針の迷いがある企業では、再出発の指針に
・方向性のズレがある場合は、意識のすり合わせに
・採用では、自社の価値観を明確にしてミスマッチを減らすために
・組織の足並みを揃え、外部からの信頼を高める
さらに、経営指針書をもとに人材育成、営業活動、マーケティング活動を遂行することで、形骸化せずに現場に“使える言葉”を浸透や定着させます。
型にハメない、でもブレさせない|私たちの支援は対話からはじまります
プラド株式会社の支援スタイルは、形式にこだわりません。
ワークショップや合宿に頼るのではなく、まずは経営者や幹部との壁打ち(対話)を重ね、価値観や意思決定の背景を丁寧に掘り下げます。
必要に応じて現場に足を運び、「この会社らしさ」が表れる日常のふるまいや空気感をつかみ、言葉として表現に落とし込みます。
それは、机上の言語化ではなく、実際の行動や空気とつながった“使える言葉”をつくるためです。
経営層と現場の言葉をつなぐ“翻訳者”として、MVV・経営指針書・中期経営計画と日々の仕事が結びつくよう調整します。
こうして生まれた言葉は、どこかで聞いたようなフレーズではなく、その会社らしい”生きた指針”として、日々の意思決定や採用・育成・マネジメントに活用されていきます。
AI時代の理念策定パートナーとして
AIで整えるだけでは届かない「経営の言葉」がある
生成AIの進化によって、文章を“それらしく整える”ことは容易になりました。
私たちも情報整理や資料作成など、AIが得意とする領域では積極的に活用しています。
しかし、経営理念やビジョン、パーパスの言語化の面では、対話でしか見えてこないものがある。とそう考えています。
「経営者の判断軸」や「迷いのない覚悟」は、対話の中でしか掘り起こせません。AIでは拾いきれない“温度”や“現場の温度感”をすくい上げてこそ、経営理念浸透・パーパス浸透・ビジョン浸透に反映できるかにかかっています。
地域ごとの文化や価値観(愛知・名古屋・岐阜・三重など)も踏まえ、対話と観察で言葉に落とし込みます。
たとえば、地域性(愛知・名古屋・岐阜・三重など)により根づいた文化や価値観があります。私たちは、経営者との対話や現場での観察を通じて、そうした“空気”まで言葉に落とし込み、その会社ならではの理念として仕上げていきます。
AIが得意なことはAIに任せる。
でも、人にしかできない“核心をつかむ対話”の部分は、これからも人が担っていくべき領域だと、私たちは考えています。
私の理念策定支援|経営者の想いを定義に落とし、言葉として組織に届ける
理念策定のプロセスでは、まず1万〜3万文字規模の情報を収集します。
経営者の言葉、事業の歩み、社員の声、迷いや葛藤の記録まで──膨大な素材から「理念のかけら」を見つけ、磨き上げます。
大切なのは、事実を拾う力と、言葉の奥にある想いを読み取る感性です。
「どの言葉に経営者の覚悟が宿っているか」「どの葛藤に本音がにじんでいるか」。
それらを見極めながら、理念・ビジョン・パーパス・行動指針・原則といった、組織を支える言葉に落とし込んでいきます。
整えた言葉は経営指針書に組み込み、必要性に応じて要約版で社内共有。
さらに、中期経営計画や四半期レビューに接続できる設計とし、運用・更新ルールまで見据えて支援します。
AIにより、誰でも「それらしい理念」をつくれる時代だからこそ──
“それっぽい理念”と、“経営者の想いが宿った本物の理念”の違いが、これからますます問われていきます。
経営者自身がどんな場面でも自信を持って理念を語れるように整える。
その理念が、組織の共通言語となり、社員の行動を後押しする。
それこそが、私たち言語家の使命です。
経営理念浸透・ビジョン浸透とは、“言葉をつくること”ではなく、“言葉で動く組織をつくること”。
この信念のもと、これからも経営者と共に、言葉の力で経営を支えていきます。
言葉の力で企業を変える
経営者の想いを、経営の言葉に
私たちが大切にしているのは、「テンプレートに頼らない言葉づくり」です。
企業ならではの哲学・情熱・覚悟を対話から引き出し、経営理念・ビジョン・パーパスとして明文化します。
定義された言葉は社内では意思統一の軸に、社外では姿勢と信頼を伝えるメッセージになります。さらに、理念を起点に経営計画・中期経営計画へ展開することで、判断に一貫性が生まれ、組織が迷わず動けるようになります。
たとえば、
・採用では共感する人材との出会いを生み、
・顧客や取引先との信頼関係を深め、
・地域との関係性やブランド形成にもつながっていきます。
そしてもう一つ大切なのが、「作って終わり」にしないこと。
経営の変化や組織の成長にあわせて、言葉の運用と更新サイクルを持ち続けることが、理念を“生きた軸”に変えていきます。
経営理念策定から始まる継続支援
浸透と実践を支えるコンサルティング|「作って終わり」ではなく、理念が生きる仕組みまで整える
経営理念やビジョン、パーパスをつくることは、経営の土台を言語化する重要な一歩です。
つくった言葉が現場で使われ、判断や行動につながる状態をどうつくるかが本当の勝負。私たちは、策定の先にある経営理念浸透・ビジョン浸透・パーパス浸透の運用設計まで一貫して伴走します。
支援の内容は、企業のフェーズや課題に合わせて変化します。
・新規事業期:パーパスと連動させ、投資判断や事業計画を言葉で整理
・急成長期:MVVを軸に、評価・育成・オンボーディングの仕組みを最適化
・組織再編期:理念・ビジョンを再定義し、経営指針書と中期経営計画を最新化
地域(愛知・名古屋・岐阜・三重など)の市場構造や採用環境も考慮し、評価制度や営業プロセスに活かせるよう策定をします。
共通して大事にしているのは、定義 → 運用 → レビュー → 改訂のサイクルを組み込み、言葉が机上論で終わらず“共通言語”として使われ続ける状態を維持します。
“言葉をつくる”ことよりも、“言葉が活きる状態をつくる”。
それが、私たちの支援スタイルです。